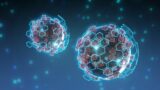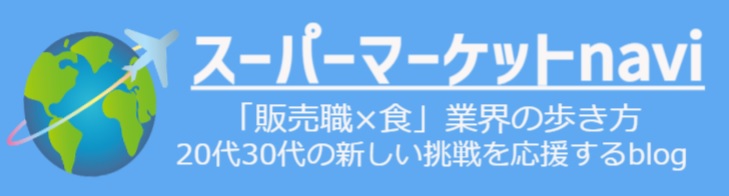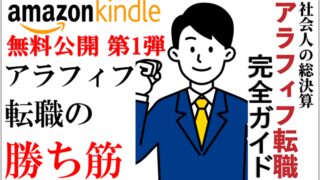今回は、スーパーマーケットのバイヤーという仕事について解説をしていきたいと思います。私もバイヤーをやっていましたので、実際の話として、業務内容を具体的に共有したいと思います。
本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで3回の転職に挑戦してきました。
✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職
地域生協(売上規模200億)から一部上場GMS(売上規模5000億)へ
全国トップレベルの惣菜売場で惣菜主任(チーフ)のスキルを獲得。
日本全国どこのスーパーでも働いていける”手に職”を得る。
✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職
一部上場GMSから県域No1シェアの食品SMへ
売場担当者 →バイヤー、店長、事業責任者へ
役職のステージアップに成功しました。
✅3度目は2024年49歳の今”ライフスタイル実現”転職
県域No1シェアの食品SMから
「家族(介護)」「趣味」「仕事」の3要素をバランスよく
実現できる、居住市No1シェアの地元密着型食品SMへ
これまでの専門性を活かし、生まれ育った地元への恩返しと
”単身赴任が無く70歳まで地元で働ける人生”にシフトしました。
タイプの違う4つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。
【X】https://twitter.com/masa_m2
2022年に業界知見をまとめた著書
「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

2024年にアラフィフ転職方法を解説した著書
「アラフィフ転職 完全ガイド」を出版しました。
★スーパーマーケット業界全体の仕事の話はコチラから★

【バイヤーの仕事①】品揃え(商品ラインナップ)の管理

バイヤーの仕事は理系の仕事が多いです(数字との格闘技)。売上構成比、利益率による相乗積(※相乗積とは、売上構成比×利益率でカテゴリーごとの利益貢献度を算出)を使って、全店の売上実績を分析しながら、対策カテゴリーを抽出し、商品を入れ替え、売上や利益を最大化していくという業務です。
バイヤーは、担当売場の商品ラインナップを管理します。
会社全体の売上→部門売上(例えば:惣菜部門)→カテゴリー売上(例えば:おにぎり・お弁当・揚物・中華・焼物など)→単品売上(例えば:○○弁当・コロッケ・○○唐揚げなど)をドリルダウンしながら販売実績を見ていき、前年と比較し落ちているところを見つけ出し、売れていない商品を売れる可能性の高い新商品に入れ替えるというようなイメージです。
商品を入れ替えられるのは登録権限を持っているバイヤーのみです。従って、世の中で売れている商品があれば、自社に登録することで売上を作ることもできますが、販売できる棚には限界がありますので、何かを登録すれば何かを外さなくてはならない、それを決定する重要な仕事です。
担当部門において何をどの棚のどの場所に販売するのかを決める、日ごと、週ごと、月ごと、季節(3か月)ごと、の綿密な商品計画を作ることで、自部門の売上と利益を最大化していく地味でありながら会社の心臓部とも言える業務です。
【バイヤーの仕事②】担当部門の利益責任
①の商品ラインナップを管理していきながら、利益管理を行っていきます。
利益とは2種類あり、商品を販売することで得られる利益と販売額に応じて得られるリベートと呼ばれる仕入先から戻ってくる利益があります。年間を通じてこれらの管理を行い、例えば途中で計画と乖離がでれば、対策を実行していく行動力も求められます。
またメーカーに依頼し自社のPB(プライベートブランド)を作ることで、通常の商品より利益率の高い差別化商品を展開するなどのウルトラCもありますし、チラシ掲載商品やその他特売商品の仕入原価を下げてもらう特売条件をもらうことも重要な仕事です。
【バイヤーの仕事③】新商品の開発

デリカ(惣菜やベーカリー)や寿司などのインストア商品は毎月新商品を開発しています。季節の味覚を使った商品がヒットする可能性が高いです。
商品開発のために関東や関西の先進企業に視察に行き、商品を実際に購入してコピー商品を作っていくのも大切な仕事です。
また、年に何度か大手卸売企業が開催する商品展示会がありますので、会場に足を運び、これから発売される商品や隠れた地方の銘品などを紹介していただき、自社に導入していくことや、
日本全国、または世界の産地にも赴き、自分が目利きした商品を導入していくこともバイヤーの醍醐味だと思っています。日本全国を巡ることができるのもバイヤーだけです。
【バイヤーの仕事④】社内コミュニケーション(部門会議や全体会議)

バイヤーは全店の部門担当者に販売状況などを聞きながら、売れない商品は終売にしたり、売れる商品を品切れしないように追加手配をかけるなど、多くのメンバーとの良好なコミュニケーションがとれる人が向いていると思います。
偉そうな態度を取るバイヤーが昔は主流だった時代もありますが、お客様の為にを実現するためには、現場の担当者さんの為に、という縁の下の力持ちに徹する意識が求められます。
月に一度、次月の商品政策をお店に伝える「部門会議」を開催し、これが売れます!これを打ってください!うらないと損ですよ~!を伝える会議があります。ここでしっかり来月の作戦を理解してもらうことが出来れば、来月は勝ったも同然です。
まとめると、バイヤーはコミュニケーション力が高い人が向いている仕事なのです。
【バイヤーの仕事⑤】季節催事
バイヤーの腕の見せ所が季節催事になります。日本には四季があり、生活に密着したイベントがあります。
1月は正月、2月は節分とバレンタイン、3月はひなまつりと春のお彼岸、4月はお花見、5月はGWと母の日、6月は梅やラッキョと父の日、7月は丑の日、8月は盆、9月は秋のお彼岸と敬老の日、10月は孫の日とハロウィン、11月はボジョレー解禁、12月はクリスマスと大晦日
季節催事にどんな商品を開発し販売できるのか?それが競合ひしめく業界での勝負の分かれ目となります。
季節催事には、その日にしか販売しない商品を販売しなくてはなりません。(例えば、バレンタインの時のみ高級チョコレートを販売するなど)
従って、ある程度店舗で季節催事にどんな商品を展開する必要があり、どのくらい売れるのかを知っておく必要があるのです。その為にも、バイヤーを目指す方は、店舗で何年か修行をする必要があることを知っておいてください。必ずそれが大切な武器となるでしょう。
「販売職×食」業界で働いてみませか?


新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。
先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。
若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。
そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、
【業界の特徴】
①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。
②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。
③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。
④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。
そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

大手企業の面接をGet「プロの転職サイト(完全無料)」を使おう

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。
なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。
企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。
しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。
無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。
悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。
おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」
【”マイナビ転職”というフレーズで有名】
成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)
20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s
未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」
こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。
アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。
↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説


今回も最後まで読んでいただき有難うございました。
今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!
スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ